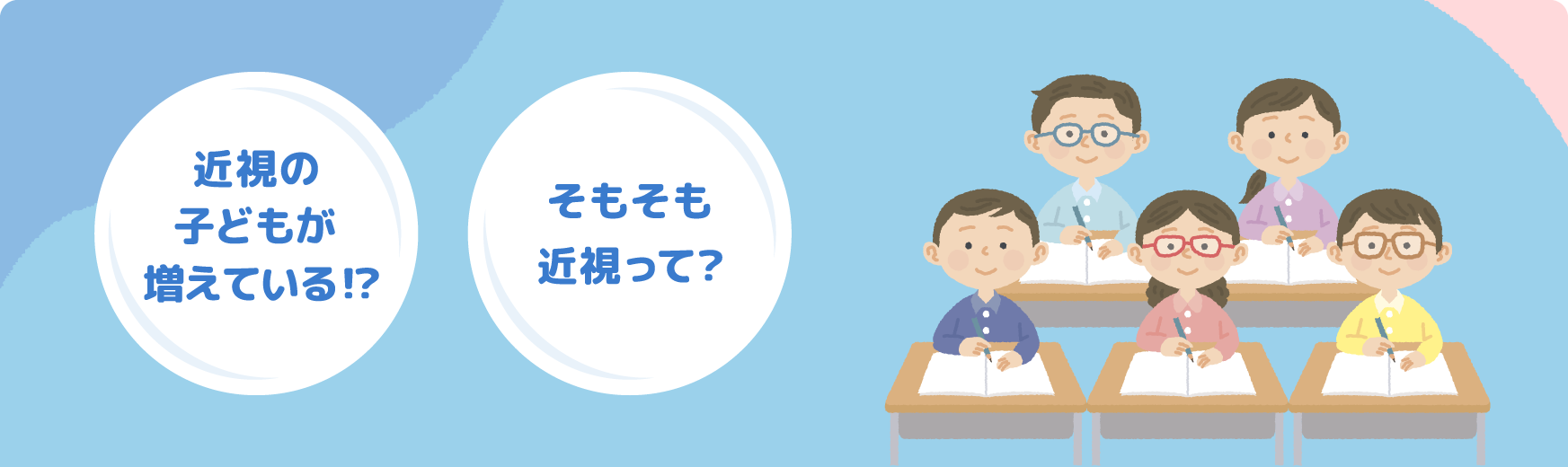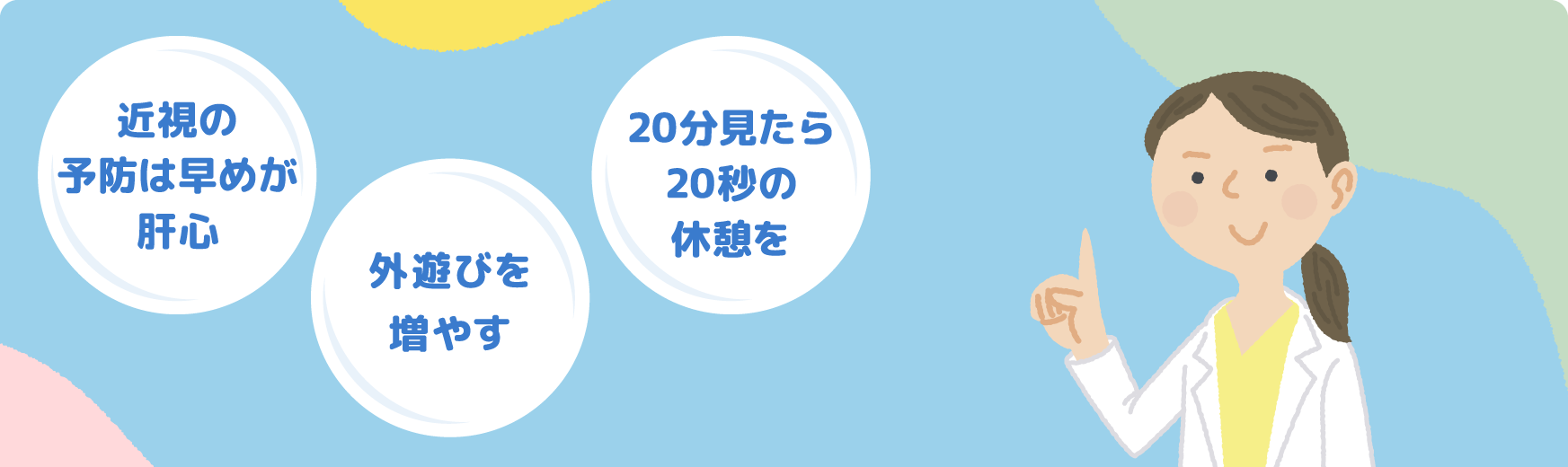2024年6月: 子どもの近視ナビ メールマガジン 第4回
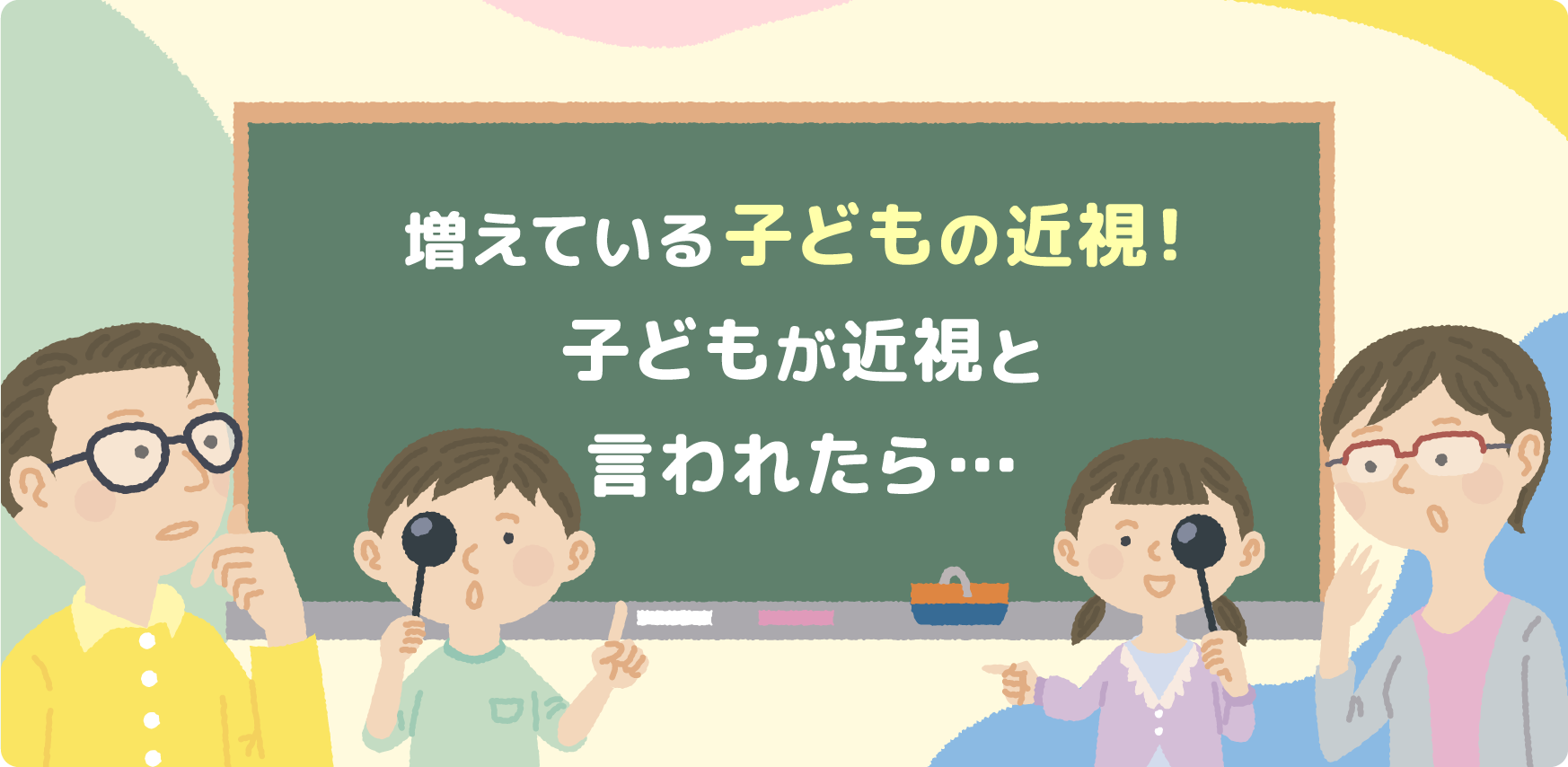
近視の子どもが増えている
今世界中で近視の子どもが増加していると言われており、特に日本を含めたアジアの地域で顕著と言われています。近視を知って、お子様の「目」にも向き合ってみましょう。
親子で学ぶ近視について
これからお子様と一緒に、近視と付き合っていくにあたり、近視のデメリットやリスクを理解しておくことが大切です。この機会にぜひ、お子様と一緒に近視を学びましょう。
近視進行の予防と対策
そもそもなるべくなら子どもを近視にはしたくありませんよね。そのためにも、毎日の暮らしを見直し、できるだけ予防を心がけることが大切です。
近視の進行を抑制するための治療法
近視はそのままにしておくと進行し、近視の度数が強くなる場合があり、また、度数が強くなると視力以外にも影響を及ぼす可能性があると言われています。近視の進行を抑える治療として効果があると言われている治療法もありますが、まずは近くの眼科で診てもらい、近視と向き合っていきましょう。
教授 大野 京子 先生
情報をお届けする予定です。
ご希望の方は、こちらからメールマガジンの
ご登録をお願いします。
個人情報の取扱いに関して
お客様からお預かりした個人情報は、クーパービジョン・ジャパン株式会社にて適切に管理し、マーケティング等の目的で個人を特定しない統計情報の形で利用いたします。
また、近視抑制の啓発活動を含めた、広告宣伝活動を目的に、情報を配信させていただくことがございます。
予めご了承の上ご登録ください。
お客様の個人情報についてはお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはございません。(法令等により開示を求められた場合を除く)
詳しくはクーパービジョン・ジャパン株式会社の「個人情報保護方針」をご覧ください。
メールマガジンに登録
クーパービジョン・ジャパンからのメールマガジンの受信を今後ご希望しない場合は、過去に受け取ったメールにアクセスしてください。
メールのフッターまでスクロールダウンし、配信停止をクリックして「配信停止」ボタンをクリックしてください。
この操作で配信停止手続きが完了したことになります。